全国福利厚生共済会は、個人向けに福利厚生を利用できるサービスを提供する、一般社団法人。
その中で注目されているのは、『お祝い金』です。
- お祝い金の種類は?
- いくら貰えるの?
- 年会費はお祝い金もらってもマイナス?
と言う部分について、調査していきます。
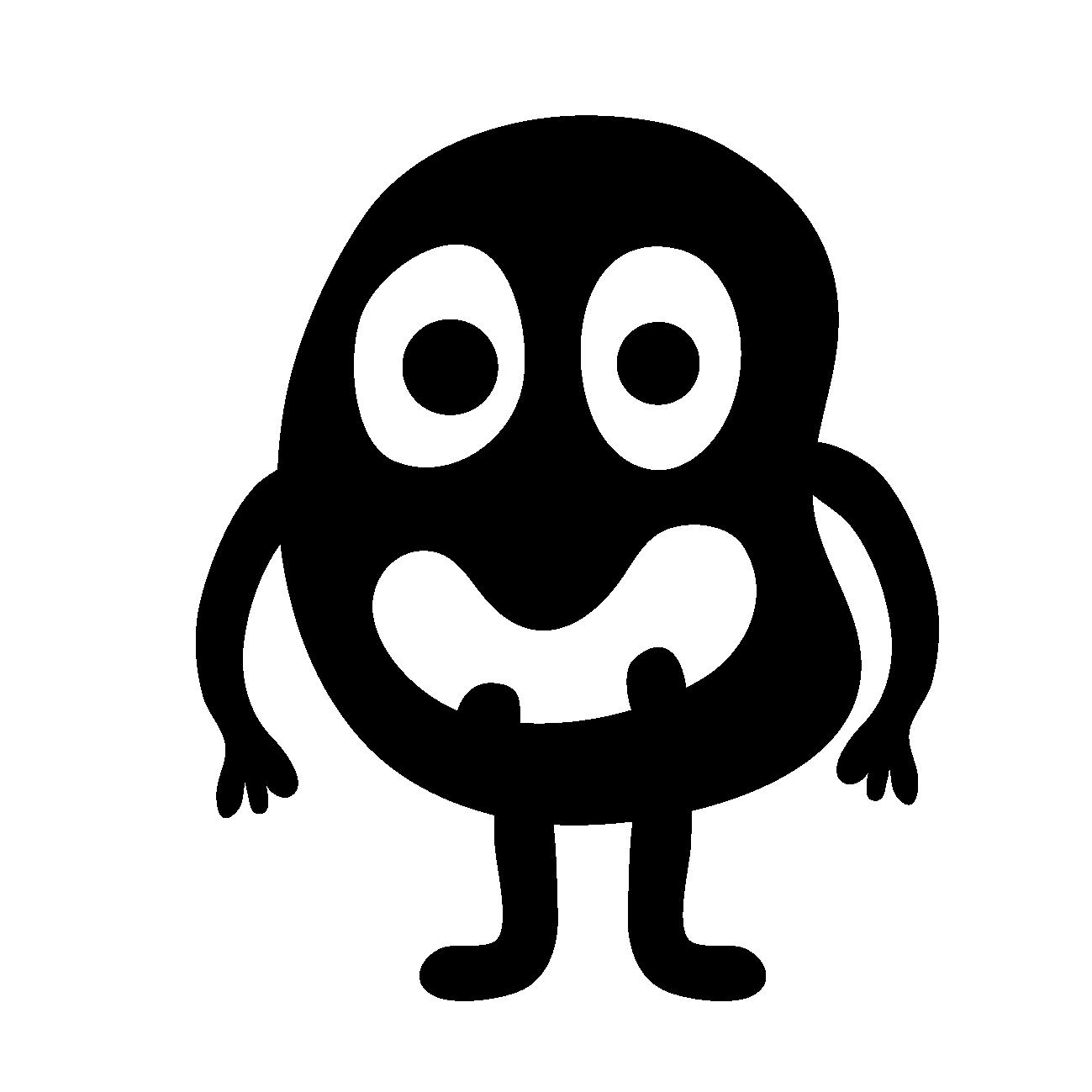
管理人は、実際に全厚済のセミナーに参加して、登録もしました。
しかし、その仕組についていくつか疑問を持っていました。
全国福利厚生共済会のお祝い金とは?

全国福利厚生共済会(全厚済)では、出産・入学・結婚といった人生の節目に「お祝い金」という形でサポートが受けられる制度があります。
これは、一般的な企業の福利厚生とは異なり、個人会員として登録している方でも利用できるのが特徴です。
しかし、お祝い金の対象となる年齢やライフイベント、さらには金額も会員種別や加入期間によって異なるため、制度を十分に理解していないと
- 「申請できなかった…」
- 「もらえると思ってたのに対象外だった」
ということも。
まずは、どんな場面でこのお祝い金がもらえるのかを確認しておきましょう。
>>全国福利厚生共済会にソフトバンク提携・割引はある?利用方法や特典まとめ
対象となるライフイベント一覧

全国福利厚生共済会のお祝い金は、以下のようなライフイベントに対して支給されます。
- 出生祝い(ゆりかご:0歳)
- 3歳の誕生日祝い
- 小学校入学祝い(満7歳時点)
- 中学校入学祝い(満13歳時点)
- 中学校卒業祝い
- 結婚祝い(会員本人の入籍)
つまり、子どもの成長に合わせた節目に加えて、会員本人の結婚も対象となっており、家族ぐるみで活用できる仕組みとなっています。
すべて申請制で、所定の申請期限を過ぎるともらえなくなるので注意が必要です。
会員種別による金額の違い

全厚済では会員種別が「P会員(プライム)」と「K会員(サービス利用者)」に分かれており、同じライフイベントでももらえる金額が異なります。
たとえば、出産祝い(ゆりかご)では以下のように差が出ます。
また、サービス利用開始から1年未満かどうかによっても金額が変動します。
つまり、「会員種別 × 加入年数」がお祝い金の金額を決定するカギになるということです。
お祝い金はいくらもらえる?年齢別一覧表

全国福利厚生共済会では、子どもの成長や人生の節目に応じて、最大3万円相当のギフトカードがもらえる制度が用意されています。
「P会員」「K会員」などの会員種別や、加入からの期間によって金額が変わるため、一覧で比較できるようにしておくのがベストです。
ここでは、ゆりかご(0歳)から結婚祝いまでをカバーした早見表を掲載していますので、ご自身やご家族が該当するタイミングをぜひチェックしてみてください。
ゆりかご〜結婚祝いまで含めた金額
まずは、お子様の成長に合わせて受け取れるお祝い金の一覧です。
対象年齢は0歳・3歳・7歳・13歳・中学卒業(15歳前後)の5段階に設定されており、条件を満たせば何度でも申請可能です。
会員のランクと加入年数によって金額が変動するため、以下の表を参考にご確認ください。
| お祝い内容 | 対象条件 | P会員・Pサービス受領者様 | K会員・Kサービス受領者様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゆりかご(0歳) | サービス利用開始から1年未満 | 10,000円分のギフトカード | 5,000円分のギフトカード | 申請期限:出生から6か月以内(例:4/5生まれ→10/4必着) |
| ゆりかご(0歳) | サービス利用開始から1年以上 | 30,000円分のギフトカード | 10,000円分のギフトカード | |
| 3歳祝い | サービス利用開始から1年未満 | 5,000円分のギフトカード | 3,000円分のギフトカード | 申請期限:満3歳の誕生日から6か月以内(サービス開始日以降の誕生日が対象) |
| 3歳祝い | サービス利用開始から1年以上 | 10,000円分のギフトカード | 6,000円分のギフトカード | |
| 小学校入学祝い(7歳) | サービス利用開始から1年未満 | 5,000円分のギフトカード | 3,000円分のギフトカード | 申請期限:満7歳の誕生日から6か月以内(サービス開始日以降の誕生日が対象) |
| 小学校入学祝い(7歳) | サービス利用開始から1年以上 | 10,000円分のギフトカード | 6,000円分のギフトカード | |
| 中学校入学祝い(13歳) | サービス利用開始から1年未満 | 5,000円分のギフトカード | 3,000円分のギフトカード | 申請期限:満13歳の誕生日から6か月以内(サービス開始日以降の誕生日が対象) |
| 中学校入学祝い(13歳) | サービス利用開始から1年以上 | 10,000円分のギフトカード | 6,000円分のギフトカード | |
| 中学校卒業祝い | サービス利用開始から1年未満 | 5,000円分のギフトカード | 3,000円分のギフトカード | 申請期限:卒業日(3月31日)から6か月以内(サービス開始日以降の卒業が対象) |
| 中学校卒業祝い | サービス利用開始から1年以上 | 10,000円分のギフトカード | 6,000円分のギフトカード | |
| 結婚祝い | サービス利用開始から1年未満 | 5,000円分のギフトカード | 3,000円分のギフトカード | 申請期限:入籍日から6か月以内(サービス開始日以降の入籍が対象) |
| 結婚祝い | サービス利用開始から1年以上 | 10,000円分のギフトカード | 6,000円分のギフトカード |
申請期限や条件に注意!見落としがちなポイント

全国福利厚生共済会のお祝い金は「申請すればもらえる」と思われがちですが、実は細かい条件や期限の設定があり、注意しないと受け取れないケースもあります。
特に見落としがちなのが「いつまでに申請すべきか」と「加入期間のカウント基準」です。
ここでは、つまずきやすいポイントを事前に押さえておくことで、もらい忘れゼロ”を目指すための注意点を解説します。
申請期限はいつまで?

お祝い金の申請期限は、それぞれのライフイベントの発生日から「6か月以内」と決められています。
たとえば…
- 出生祝い:出生日から6か月以内
- 3歳・7歳・13歳の誕生日:各誕生日から6か月以内
- 中学校卒業:卒業日(3月31日想定)から6か月以内
- 結婚祝い:入籍日から6か月以内
この「6か月以内」に、“書類が到着していること”が必須条件となるため、ギリギリの申請はリスクが高いです。
郵送の遅延なども想定して、1〜2週間前までには手続きを済ませるのが安心です。
“利用開始日”がカギになる理由

もうひとつ重要なのが、加入日ではなく「サービス利用開始日」が基準になるという点です。
たとえば、登録は済んでいても、サービスが実際に有効になった日が基準日となるため…
- 誕生日や入籍日がサービス利用開始日より前だった場合 → 対象外
- 利用開始から1年未満かどうか → もらえる金額が変わる
つまり、「自分は加入してるし大丈夫」と思っていても、開始日を勘違いしていると申請自体が無効になることも。
マイページや案内書類で“利用開始日”を必ず確認してから、申請スケジュールを立てましょう。
まとめ|お祝い金は嬉しいが申請は計画的に

全国福利厚生共済会のお祝い金制度は、子育て世代やこれから結婚する方にとって、確かに魅力的なサポートです。
しかし、もらえるタイミングや金額には「条件」と「期限」があり、計画的に申請しなければそのメリットを受け損ねてしまう可能性もあります。
ここでは最後に、年会費とのコストパフォーマンスや、実際に利用してみた管理人の感想をまとめました。
年会費とのバランスをどう考える?
お祝い金の制度は確かにありがたいですが、見落とせないのが年会費の存在です。
例えばP会員の場合、年間の会費は約5万円前後(※プランによって異なる)で、これに対して最大で3万円のお祝い金が受け取れる可能性があります。
一見すると損に見えますが、「条件を満たす」「期限内に申請する」というハードルをクリアして初めて成立する話。
※管理人は、ガソリンの割引サービスや飲食店のクーポンなども利用しています。
逆に、1回も申請しなかったり、申請漏れがあった場合には「会費を払って終わり…」なんてことも。
お祝い金を確実に活用できる見込みがある方にとってはお得な制度ですが、そうでない場合は慎重な判断が必要です。
管理人が感じたメリット・注意点
実際にセミナー参加と登録をした管理人として感じたことは、以下のような点です。
メリット:
- ライフイベントが多い家庭にとっては、高確率で元が取れる
- 申請さえすれば、現金に近い形でギフトカードがもらえる
- 個人でも企業並みの福利厚生が受けられるのは魅力
注意点:
- サービス開始日や加入年数をきちんと把握しておかないと損をする
- 説明がやや複雑で、初見では理解しづらい部分がある
- セミナーや案内資料が“ちょっと熱量高め”で合う合わないがある
制度自体は良いのに、情報が整理されていないせいで損をする人が多そうだな…と感じました。
この記事が少しでも「損しないための参考」になれば幸いです!
「創業者の人物像は こちら に詳しくまとめています。」
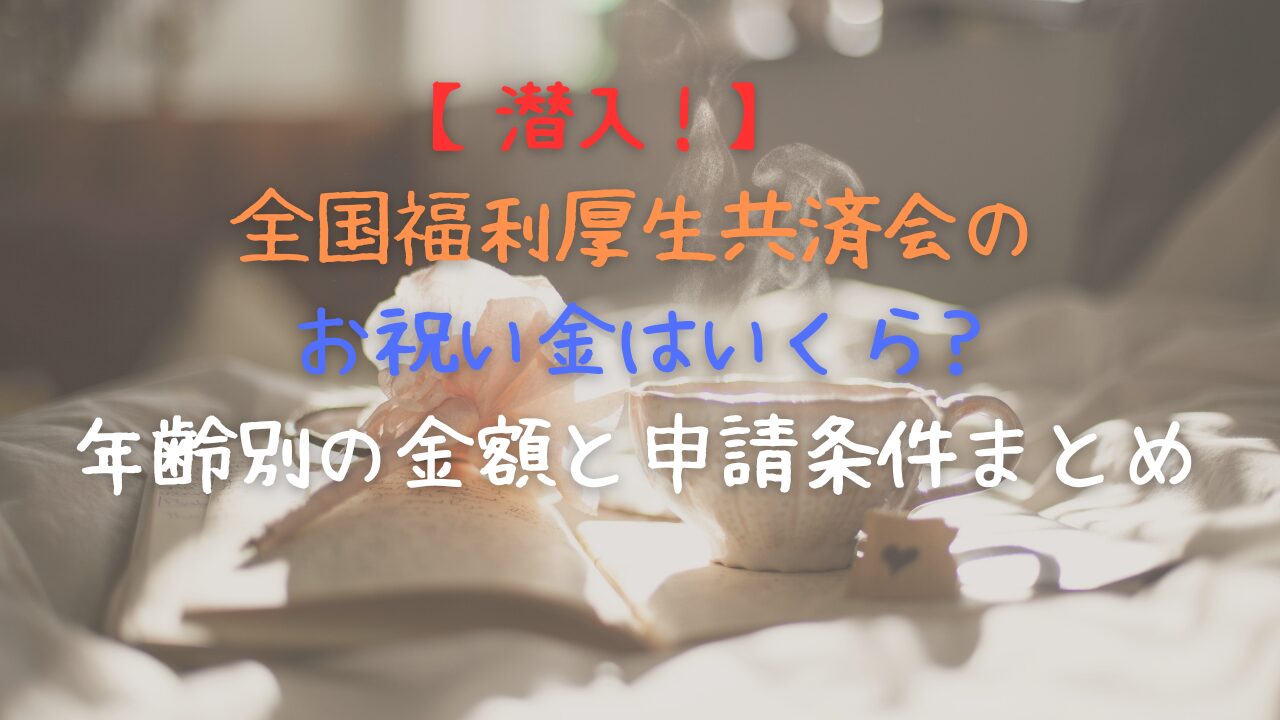
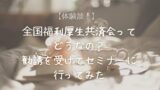
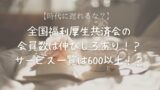
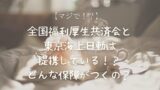

コメント